こんにちは!製薬企業で研究職として勤務している、tabeと申します!
就職活動では博士学生として様々な製薬企業から内々定をいただき、
当ブログにて、そのノウハウや役立つ情報を発信しています!
さて、当記事のトピックは「製薬企業の求める博士人材像」です!
そのため本記事は、大学院進学で悩む学部や修士、キャリアに悩む博士課程の学生さん向けです。
様々な意見があるかと思いますが、「医療用医薬品メーカーの研究職」に限ってしまえば、
博士は正しくアピールできれば修士と同等、あるいはそれ以上に就職しやすい傾向にあります。
私個人としては間違いないと思っています。
しかしあくまで傾向です。内々定の可能性を高めるためにも、
現場が「博士」に欲する能力を必死に磨き、そしてアピールする必要があります。
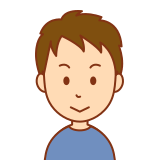
就活書類の自己PRが上手くかけているか不安…
博士に期待していること?専門性?
博士課程で学んだ何をアピールしたら良いんだ…??
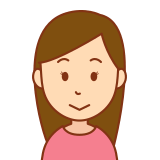
博士に行くか悩む…
博士に入ったら何を意識して取り組もう。
社会は博士に何を求めているの??
そんな疑問や不安、少しでも払拭していただければ幸いです!!
それでは早速、内容に入っていきましょう!
結論、研究者としての即戦力を求められます!
製薬企業が博士に求めること。一言で表現するならば、「研究者として即戦力か否か」です。
ここは、修士で入社された方々との差別化を図る、大変重要なポイントです!
くりぷとバイオさんの上記事にもありますように、
修士で入って入社4年目の方と比べられると、博士はビジネス感覚では勝てません。
この事実は私も痛感しています。(できるだけ早く追い越したいとは思いますが。。)
ではどうするか? 結論は、研究で勝負するしかない。
我々は修士の方と違い、3年間「研究」をより主軸に生きてきたわけです。
ここにはプライドと実力を持っていて欲しい。
そして、製薬企業で「即戦力」となるために大切なポイント、具体的に3つ紹介したいと思います。
自分で課題を設定し、それを解決できる
私が入社して感じた、自分に求められているなと感じたことが「課題を設定し、解決する力」です。
目前の研究、一体何故止まっているのか。何を解決するとブレイクスルーなのか。
おそらく博士の学生なら、嫌というほど考えてきたはずです。(笑)
実際に面接では、研究内容への興味だけでなく、
どうやって研究を展開してきたのか、ここにかなり興味を持っていただけます。
(こちらの記事でも紹介しています。)
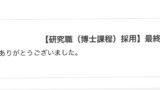
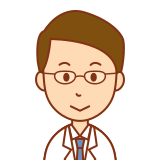
研究で行き詰まったときにどうやって解決していますか?
この質問の意図は、
「適切な課題をどう見極め、どうやって解決しますか?(入社後出来ますか?)」ということです。
ぜひ博士課程では、課題の設定を自分で積極的に行うこと、
そして、どうやったら解決できるのかを考え、行動に移し、実際に解決した経験を積むこと、
これらを大切にし、就活でもアピールしていただければと思います。
何でも教員にすぐ相談…そんな自分とはサヨナラしましょう!!
専門性も大切だが、専門外を専門領域に変える力も大切
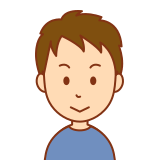
博士課程の強み…「専門性」だ!!
と飛びつくことは、少し危険です。
もちろん企業側が求める領域でマッチングがあれば、それに越したことはありませんし、
特に医療用医薬品メーカーでしたら、ある程度の専門性のマッチングも大切です。
しかし実際は、私が内々定を頂いたのは、専門性のマッチングがあった領域ばかりではない。
むしろ半分は、自分の興味のある研究領域を志望し、内々定を頂いています。
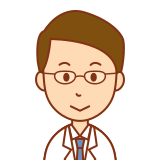
tabeさんには○○で活躍してほしいのだけど、
本当にこっちの部署が良いの??
そんなことを面接中聞かれたこともあります。が、無事に希望通りの部署から内定をいただけました。
必ずしも、専門性ばかりを見ているわけではないと言えます。
博士だからこそ「専門に拘る」のではなく「どんなことでも専門に仕上げられる」こと、
私が就活中にも大切にしたこの意識をぜひ持って、博士課程を過ごして下さい。
あくまで博士課程の研究内容は、貴方の研究力を伸ばすためのものです。
研究で必要な語学力は十分に備えてる
語学力、想像以上に、直ぐに求められます。
論文を読むことは当たり前。メールでの対応や英語での会議など、
場合によってはかなり早い段階から求められることもありそうです。
記事で詳細に紹介しましたが、就活中にあまり語学力を聞かれることはないです。
ただし、実際に現場に入ると、すごく求められる能力だなと感じます。

学生のうちに、ぜひ国際学会や論文執筆を少しでも多く経験しておいたほうが良いですよ!!
(3年前の自分に、本当に言ってやりたいものです。苦笑)
まとめ
博士は就職が難しいのでしょうか??
いえいえ、我々の意識と努力次第で、そんなもの、どうにでもなります。
むしろメリットにすら出来る。
これが私の結論です。もちろん、社会の博士への理解もまだまだ追いついていないでしょう。
しかしそれは、我々博士側のアピールの仕方にも問題があったと感じます。
専門性ばかりを主張することは、社会のニーズには必ずしもマッチしていません。
製薬企業を皮切りに、一部化学メーカーなど、徐々に博士を受け入れる体制は整いつつあります。
また、以前ツイッター上でノブさんと少しお話させていただきましたが、
企業だけでなく、未だ知られていない博士の活躍の場も必ずあると思います。
ぜひ博士の方々で、日本を盛り上げていきましょう!!
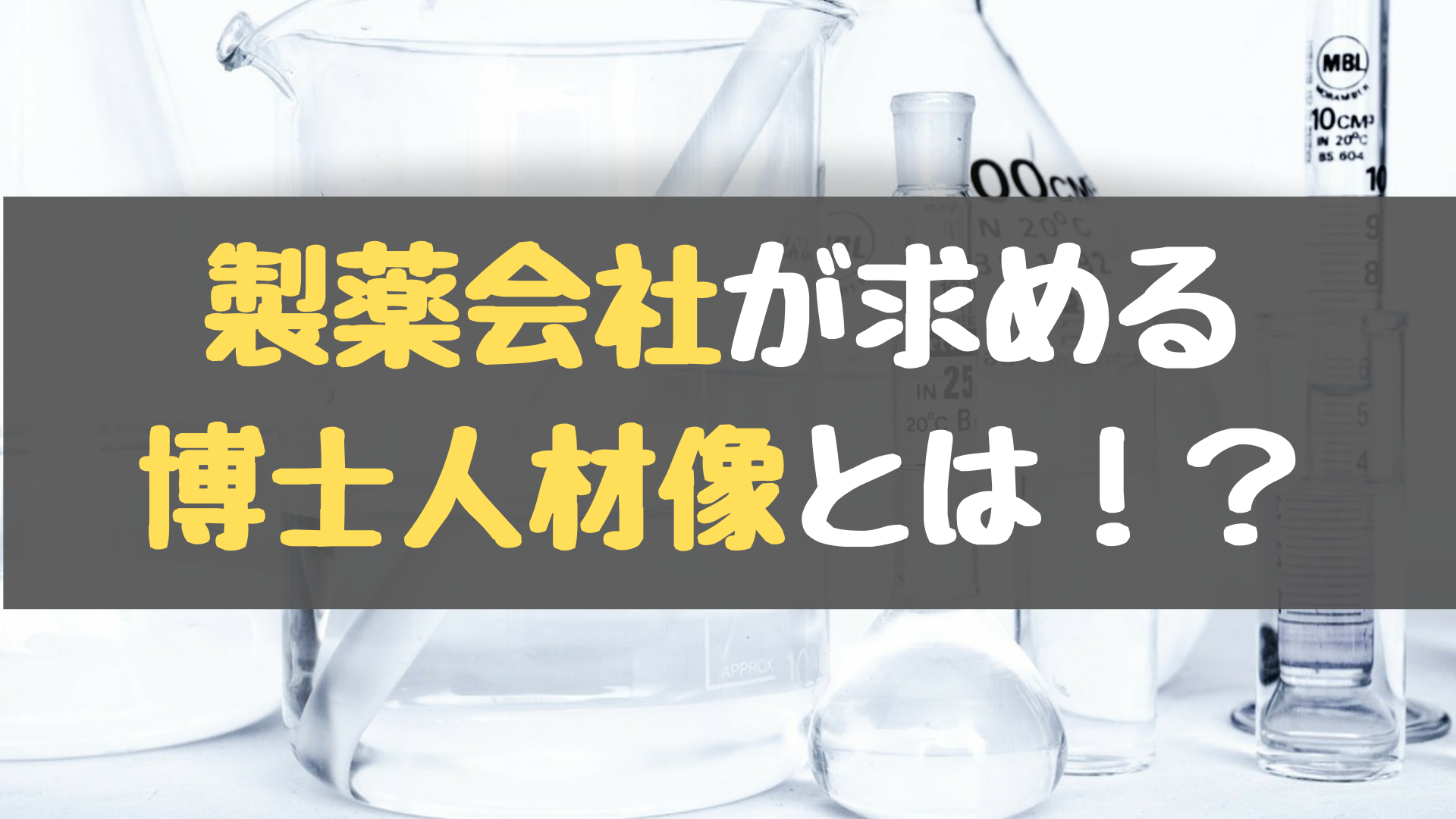

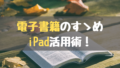
コメント