医薬品にも様々な種類があるのをご存知でしょうか。
代表的な分類は、「低分子医薬品」「高分子医薬品(抗体医薬品)」ですが、
中分子医薬品(ペプチド医薬・核酸医薬他)、細胞医療(再生医療・CAR-T他)、PROTACなど、
様々な医薬品・医薬品候補が登場しています。
業界用語では、各カテゴリーのことを「創薬モダリティ」とも呼んでいます。
製薬企業は治療したい疾患に合わせて、適切なモダリティを選択しています。
つまり、それぞれのモダリティの長所・短所を明確に理解することは、
各製薬企業の目指す方向性を知るきっかけになると考えています。
そこで当記事では、有名所の高分子・低分子を中心にまとめたいと思います。
*新たに核酸医薬に関する書籍が出ていましたので、こちらで解説しました。
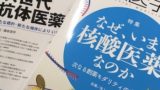
低分子医薬品
まずは何より、有機合成によって作りますので、高分子と比べると製造コストが安い傾向があります
(実際には、日本では製薬企業は薬価を自分で決められないので安価で提供できる保証はないです。)
また、小さな分子であるため細胞内にも届けることが出来ます。
つまり創薬ターゲットとなる分子が細胞質に存在していても、低分子であれば標的にすることが出来ます。
さらに、胃や腸で分解されず血中へと運ぶことも可能であり、手軽な経口投与との相性が抜群です。
その一方で、後ほど登場する抗体医薬品と比べると、
特異性の低さ(副作用の出やすさ)や分解の受けやすさが指摘されています。
物質そのもののサイズが小さいため、狙いたい標的のポケットサイズが大きすぎると、
創薬標的の対象外になることもあります。
(そのため、酵素の活性中心をピンポイントで狙うような化合物が多いです。)
また、低分子医薬の時代が長く続いたことから、
創り出せるレパートリーに限界が来ている、という指摘もチラホラ聞きます。
ただそう言われてからかなりの時間が経過しますが、未だに創薬研究の主流であることに間違いありません。
まとめ
長所
・製造コストを抑えられる
・細胞内・細胞外いずれの標的分子にもアクセスできる
・投与方法にバリエーションがある
短所
・得意性が(比較的)低い
・半減期が短い
(・有機合成できるレパートリーが枯渇している?)
高分子医薬品(抗体医薬品)
高分子医薬品の代表は、抗体医薬品です。
抗体は特異性が極めて高いことから、副作用の少ない医薬品とされています。
また血中における高分子医薬品の半減期は低分子と比べて長く、
一回の投与で長時間の投与効果が期待できます。
ここまで聞くと低分子より圧倒的に魅力的ですが、デメリットもいくつか言われています。
まず、高コストであること。
抗体は有機合成ではなく、抗体の遺伝子を導入した細胞を培養し、
その培養上清から有効成分だけを精製することで得られます。
大掛かりな施設を要し、細胞培養などコストの掛かるステップを経るため、
研究にもかなりのコストが掛かるのです。
さらに抗体はタンパク質であるため、経口投与を行うことが出来ません。
口から入れてもすぐに胃で分解されてしまうためです。
そのため静脈注射(点滴)などで投与する必要があります。
(この事実が意味するところは、主に病院で医師から直接受ける治療手段になる、ということです。)
また最後に、抗体は血中を巡りますが、細胞質側に移行して機能を発揮することは出来ません。
ですので、標的分子は細胞表面タンパク質か、血中に存在する分泌タンパク質に限定されます。
標的のサイズは低分子化合物よりも大きなものでも対応可能で、
抗体のFc領域に薬物を乗せるなどDDSとしての応用も様々実施されています。
本記事では詳しく述べませんが、
ペプチドなど中分子化合物は「細胞の中も狙えて標的サイズも大きくてもOK!」と期待されています。
(それほど単純ではないようですが…。)
まとめ
長所
・得意性が高い(副作用が少ない)
・半減期が長く、長時間の投与効果が見込まれる
短所
・比較的高価である
・標的分子に限りがある
・経口投与が出来ない
疾患に合わせてモダリティを選択している具体事例
少し具体的な話をさせていただき、当記事を終えたいと思います。
(ここまで単純化することも難しいのですが、例えば以下のように考えることも出来ます。)
中外製薬と抗体医薬品
例えば抗体医薬品を強みとする中外製薬ですが、重点領域の一つは「がん」です。
この組み合わせはすごく理にかなっています。
がんのように、長期にわたる治療(投与効果)が必要で、特異性の高い医薬品が好まれる疾患では、
上述したメリットを持つ抗体医薬品との相性がすごく良いと考えられます。
病院での診断後、入院しつつの治療が多いため、点滴投与との相性も悪くありません。
塩野義製薬と低分子医薬品
低分子医薬品を強みとする塩野義製薬の重点領域の1つは「感染症」です。
感染症にかかったとき、軽症であれば病院に入院することはせず家で治療をしたい。
そんな疾患に対しては、点滴でしか投与できない抗体医薬品は場合によっては相性が悪く、
経口投与で自ら服用できる低分子医薬品が活躍します。
昨今開発されたゾコーバも具体例の一つかもしれません。
実際にはここまで単純ではなく、
疾患毎、そして疾患を抱えておられる患者さん一人ひとりに異なるアンメットニーズがあり、
製薬企業はどのようなプロファイルの製品であれば使っていただけるかを日々試行錯誤しています。
志望企業が強みとしている創薬モダリティの本質を考えるきっかけにしていただければ嬉しく思います。
以上となります、他の記事も参考にしつつ、実りある就職活動にしてください。

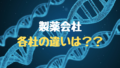
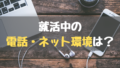
コメント